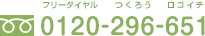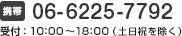会社のロゴ作成で気を付けたい!著作権について知ろう
起業・開業、新サービス開始などにともない新たに会社のロゴを作成する場合、長く安心してロゴを使用するためには、著作権をはじめとする権利関係の対策を万全にしておくことが重要です。
よく知られている権利として「著作権」や「商標権」ありますが、なんとなく理解しているつもりでも、うっかり他者の権利を侵害していたり、知らぬ間に権利を侵害されていたりするケースが珍しくありません。最悪のケースでは、係争問題に発展する場合もあるので、会社として大切なロゴを長く安心して使用していくために、ロゴ作成とセットで権利関係についてもしっかり確認しておきましょう。
今回は、会社のロゴ作成時に気を付けたい「著作権」について、まとめました。ぜひ依頼時の参考にしてください。
目次
会社ロゴの「著作権」とは?
ここではまず、著作権とはどんな権利を指すのかを解説します。
著作権とは、「著作者」(著作物を作成した人)が著作物を独占的に利用できる権利のことをいい、特別な手続きがなくても著作者に対して自然発生します。
著作物は作者の考え(思想)や気持ち(感情)を表現したもののことを指し、学術・文学・美術・音楽の分野で著作者を守るために設定されている大切な権利です。
プログラムや建築物、地図、図形なども著作物に含まれており、会社やサービスのロゴも例外ではないため注意しましょう。
全てのロゴに著作権が発生するわけではない
ロゴにもさまざまな種類がありますが、すべてのロゴに著作権が発生するわけではありません。
ここでは、大きく以下のように3つに分類してお話していきます。
- シンプルな文字列のみのロゴ
- 文字+シンボルマークのロゴ
- シンボルマークのみのロゴ
①のシンプルな文字列のみのロゴの場合、係争問題に発展した場合に著作権が認められないことがあるので注意しましょう。過去の事例では、大手飲料メーカーが使用する文字列のみのロゴに著作権が認められなかったケースがあり、その際には「デザイン的な工夫はあるものの独創性がない」と判断されています。
一方、②の文字+シンボルマーク、③のシンボルマークのみといったロゴの場合は、シンボルマークに著作者の思想が反映されることが多いため、著作権が認められる可能性が高いです。
著作権には2種類ある
著作者の権利を広く守るために、著作権には「著作権(財産権)」と「著作者人格権」の2つの種類があります。次はそれぞれについて、少し細かく見てみましょう。
◆著作権(財産権)
著作権(財産権)は、著作者の財産的な利益を保護する目的があります。
そのため、著作物を販売・複製する・営利目的で公開するなどの場合には、著作者に許可を取ったうえで使用料を支払う必要があるため、企業・サービスのロゴ作成の場合には特に注意したい部分です。
◆著作者人格権
著作者人格権は、著作者の人格を保護する権利です。
著作物のタイトルや内容は勝手に変えることができず、著作者を公表する・しないについて、もし公表する場合にはその名義についても、著作者が指定したとおりでなければいけません。
会社のロゴを作るなら著作権が譲渡されるか要確認!

これまで著作権について理解を深めてきましたが、実際に会社のロゴを作る際、そのにロゴの著作者は誰になるのでしょうか。
もし、社員がロゴを作成した場合は、条件を満たせば社員が所属する会社に著作権が認められますが、会社のロゴを作る際、ほとんどの場合は専門業者に依頼します。その場合、依頼した会社側(発注側)には著作権が認められず、実際にロゴ作成を行ったデザイナーまたは制作会社が著作者になります。そのため、ロゴ作成を依頼する場合には、著作権の譲渡についても事前に確認することが大切です。
ここでは、会社のロゴ作成を依頼する際に気を付けるべき著作権の譲渡について解説します。
著作権の譲渡に関するメリット・デメリット
ロゴ作成の著作権では、実際にロゴを活用する場面で、著作権を譲渡しているかどうかによって業務上の負担が大きく変わってくる恐れがあるので、十分に注意しましょう。
ロゴの著作権が制作会社にあるままの場合、契約内容によっては、せっかく作成したロゴも自由に使用することができないかもしれません。
例えば、ロゴを使用した商品を販売したい場合、ロゴの使用について著作者の許可が必要になったり、その都度ロゴの使用料の支払いを求められたりする場合もあります。
その他、ものやサービスによってロゴの色を変更したい場合などにもロゴの変更について著作者への相談や許可が必要になるケースがあります。そうすると、業務上のあらゆる場面でロゴの使用・変更に関する許可取りや、使用料の負担が重くのしかかってきます。
ロゴ作成時に著作権の譲渡を済ませることでこれらの心配や負担を一気に解消することができ、自由にロゴを使用できるうえ色や形を変更することも可能です。
しかし、著作権の譲渡を行った場合にも「著作者人格権」については譲渡されないため、いくらロゴの変更が可能になるからと言っても著作者の人格・作品の名誉が保護される形で使用するよう注意しましょう。
著作権の譲渡は制作会社によってさまざま
ロゴ作成では著作権譲渡が非常に重要であることはおわかりいただけたと思いますが、著作権譲渡に関する対応は依頼する制作会社によってバラバラなのが現状です。
著作権譲渡に別途料金を設けている会社もあれば、そもそも著作権譲渡を行っていない会社もあります。この別途料金も金額に幅があり、5~10万円程度の料金を設定している場合もあるので、依頼前にしっかり確認しましょう。
会社ロゴの作成場面では必須ともいえる著作権譲渡ですが、これに対するスタンスは依頼する業者によって異なることを十分理解しておくことも大切です。
◆LOGO市なら著作権譲渡も込みの料金で安心!
ロゴ作成会社のLOGO市では、ロゴの著作権譲渡について別料金を設けていません。
ロゴは、完成したらお客様にどんどん使っていただいてはじめて役立つものだという考えから、すべてのご依頼について著作権の譲渡まで含めて「ロゴ作成」としています。
会社ロゴの著作権譲渡に証明書は必要?

著作権の譲渡について、制作会社ごとに対応がかなり異なることはおわかりいただけたと思いますが、著作権譲渡の表明についても対応が異なるのが現状です。
著作権譲渡証明書の発行にかかる料金もそれぞれの会社が設定していますし、そもそも著作権譲渡証明書を発行していない場合もあります。
ロゴ作成と同時に著作権譲渡さえしてもらえれば、証明書は必要ないのでしょうか?
ここでは、著作権に関する譲渡証明書について解説します。
著作権に関する譲渡証明書は後々のトラブル回避に有効
著作権に関する譲渡証明書は、著作権の譲渡が行われたことの証明になる文書のことで、著作権譲渡に関わる条件などがある場合はその条件などが記載されています。
著作権は著作物に対する重要な権利ですので、この譲渡が適切に行われたことの証明になる重要な文書であると考えてよいでしょう。
ロゴ作成を依頼する場合、メールなどの記録に残る形で著作権譲渡についてやり取りすることもありますが、万が一のトラブルに備え、書面もあるとより安心です。
特に、会社のロゴとして使用する場合、安心して長くロゴを使用し続けるためにも著作権に関する譲渡証明書を発行しておくと良いでしょう。
◆LOGO市では著作権譲渡証明書の発行にも対応!
LOGO市では、納品時に作成したロゴの著作権を譲渡しており、ご希望があれば著作権譲渡証明書の発行も可能です。(オプション対応)
実際に企業のロゴ作成をご依頼いただく際は、多くの場合で著作権譲渡証明書を発行されています。せっかく作成した会社ロゴですから、長く安心してお使いいただくためにも著作権対策は万全にしておくとよいでしょう。

「著作権」と「商標権」の違いは?
ここまで著作権について解説してきましたが、ロゴに関係する権利としてもうひとつ「商標権」があります。
著作権と商標権は似ているようにも感じますが、どのような違いがあるのでしょう?どちらも会社のロゴにとって大切な権利です。
ここでは、「商標権」についての解説とともに、著作権との違いについてもまとめていきます。
商標権とは?
ここではまず、商標権がどのような権利なのかを解説します。
商標権は、商品やサービスについての商標を保護する目的で認められた権利で、ロゴなどを商標として登録することで商標権を主張することができます。
商標の登録は特許庁への申請が必要で、著作権のように権利が自然発生するわけではないので注意しましょう。
また、商標はロゴなどのマークとサービスがセットで登録されるので、複数のサービスで権利を主張するためにはそれぞれの商標登録が必要なので、こちらも注意が必要です。
商標権は5年または10年ごと(選択可能)に登録を更新すれば半永久的に権利を主張できることも特徴のひとつで、著作権の場合は著作者の死後から原則70年、または法人など団体が著作者の場合は公開から70年と期間が定められており、保護期間が終了したら著作権は消滅します。
「著作権が譲渡されている=商標登録できる」は間違い!
会社ロゴの商標登録を検討する際、どのような条件で著作権が譲渡されているかも重要になってきますが、下記内容が著作権譲渡証明書や契約書に記載されていれば、商標登録の申請ができる可能性が高いでしょう。
- 「著作権はすべて依頼者に譲渡する」旨の記載、又は「著作権の全範囲について使用許諾する」旨の記載
- 「著作者人格権を行使しない」旨の規定
- 「商標登録出願できる」旨の記載があればなおよい
上記の内容が著作権譲渡証明書や契約書に記載されていない、もしくは著作権譲渡証明書や契約書を取り交わしていない場合は、念のため、依頼したロゴ制作会社に、商標登録の申請について相談・確認するのをおすすめします。
また、「オリジナルロゴ=商標登録が可能」ということではありませんので、会社としてより一層、権利関係を明確に、そして安心して長くロゴを使っていきたいのであれば、あらかじめ商標登録を前提としたロゴ作成のサービスを活用しましょう。
◆商標登録とロゴ作成ならLOGOPLUSで対応可能!
ロゴ作成とセットで考えることの多い商標登録ですが、商標登録には事前の商標調査や登録申請に向けての手続きなどの細々した作業も必要になってくるため、苦労されているお客様が多くいらっしゃいました。
LOGO市では、そのようなお客様の声をもとに、ロゴ作成から商標登録までをまるごとサポートする「LOGOPLUS(ロゴプラス)」というサービスもご提供しています。
ロゴデザイン会社と商標登録のプロフェッショナルである特許商標事務所がタッグを組み、お客様の利権とブランドを守るための商標をご提案しますので、商標登録も見据えたロゴ作成をお考えの際は、ぜひお問い合わせください。
会社のロゴを安心して活用していくために…ロゴの著作権は譲渡してもらいましょう
今回は、会社のロゴ作成で気を付けたい「著作権」について解説してきました。
ここまでの内容を簡単にまとめると…
- ロゴ作成を依頼する際は、著作権が譲渡されるのか事前に確認しましょう!
- 著作権の譲渡を行ったら「著作権譲渡証明書」も発行しておくとさらに安心!
- 著作権と商標権は別物!
- 会社のロゴを商標登録して活用していきたいなら、ロゴ依頼時に相談&専門のサービスを使いましょう!
会社や商品のイメージを表現したり、目印として広く目につきやすいロゴだかこそ、「著作権」と「商標権」について最低限理解した上で、権利関係もしっかりしている制作会社にロゴの作成を依頼すると良いでしょう。トラブルが起こるとそれ以降、そのロゴを使えなくなってしまう場合もあり、会社として大きな問題となる可能性も否めません。ロゴ作成を依頼する段階で事前にできる対策をしっかりと行うことで、将来に起こりうるトラブルを回避できるように意識しましょう。
LOGO市では、ロゴ作成に関わる「著作権」や「商標権」について、経験豊富なスタッフが丁寧に対応させていただきます。大切な会社のロゴですから、ロゴの権利関係についてご不明点があれば、お気軽にご相談ください。