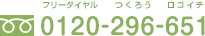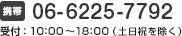はじめてのロゴ作成!初心者でもこれさえ読めばできるロゴの作り方
ロゴ作成といえば何から手を付けたらよいのか分からない人も多いでしょう。しかし、作成のコツさえ掴んでしまえば、初心者でも作成することは可能です。しかし、ただ感覚だけでは、ターゲットに訴えるロゴとはなりません。今回は、はじめてのロゴ作成でも使える、全くゼロから印象に残るロゴを作る方法を、順を追ってご紹介します。
はじめてのロゴ作成!作り方のコツは?

はじめてロゴを作る場合、まず何から始めたらよいのか、どういう手順でロゴをイメージしていけばよいのかがわからないかもしれません。そこで、ロゴを考える場合に、最初に押さえるべきコツをご紹介します。
まずはターゲットを考える
まずは、ロゴでどのような層を狙うのかを考えていく必要があります。たとえば、男性や女性、年齢層、職業など、最もサービスを利用してほしい人を明確にしていきます。ターゲットによって、ロゴの雰囲気は異なってきますので、できるだけ具体的に要素を上げておきましょう。
そして、ロゴをどのような雰囲気に仕上げるかをイメージします。たとえば、女性向けならかわいい感じのロゴ、若い人向けであるなら、スタイリッシュでシャープなイメージ、といった具合です。細かい部分は、次のロゴのテイストを考える際に絞り込みますので、漠然としたイメージで構いません。
また、ロゴを考える際には、文字だけでなく、食べ物など、会社や商品に関係するモチーフを入れるようにすると、ターゲットに響くロゴを作ることができます。こちらも簡単でよいので、合わせて考えておきましょう。
次にロゴのテイストを考える
ターゲットを考えたら、次はロゴのテイストを考えていきます。テイストを決めるときによく使われる方法は3つあります。いずれの方法でも、ロゴのテイストを考える場合にはまずシンボルを定めるとイメージがまとまりやすくなります。
まず1つ目は、ターゲットから連想されるテイストを次々と書き出していく方法です。ターゲットに関係するキーワードを拾い出し、そこからさらに連想されるキーワードをどんどん書き出していきます。そして、出てきたキーワードを組み合わせながら、テイストを絞り込んでいくという手順です。キーワードの組み合わせはシンボルマークのヒントにもなりますので、ターゲットのイメージと離れてしまわないように注意しましょう。
2つ目は、連想です。ターゲットから連想される言葉を書き出します。1つ目の方法ともよく似ていますが、こちらの方がシンプルな方法です。複数のイメージを広げるというよりも、ターゲットを核として、直接関連するキーワードを上げてイメージを広げていきます。
3つ目は、置き換えです。書き出しや連想でよいイメージが浮かばなかった場合に、ターゲットを物や人に置き換えてみて、テイストをイメージします。飛躍しがちですが、新しい発想のロゴを考えたいときには効果的な方法です。
◆ロゴについての知識も大事
ロゴを作成するにあたり、ロゴに関する知識も最低限知っておきましょう。
こちらに、はじめてロゴを作成する人にも役立つ情報をご案内しています。

手書きでスケッチ
ロゴのテイストが決まってきたら、まずは手書きでイメージのスケッチを行いましょう。このとき、丁寧に書く必要はありません。最初から形にすることは難しいため、どんどん書いてみてください。
そして、できるだけ多くのデザインを出しましょう。頭の中でイメージするよりも、実際に書いてみる方が明確にデザインに落とし込むことができるはずです。
パソコンでのロゴ作成
手書きである程度デザインの案が具体的になってきたら、パソコンで作成をはじめましょう。パソコンでロゴを作る際には、Adobe Illustratorなど、ベクターデータを扱えるソフトを使用するのがおすすめです。ベクターデータは、点や線でできているため、サイズを変更してもデザインや画質が変わってしまうことはありません。作業環境に合わせたソフトで作成しましょう。
パソコンでロゴ作成を始める際、1からデータを作るのは手間がかかります。手書きしたスケッチをスキャナや写真でパソコンに取り込み、トレースを行うのがおすすめです。トレースしたスケッチを元にソフトで線や図形などを作成して、ラフデザインをデータにしていきます。
ラフデザインのデータができあがったら、1つのデザイン案に対して、複数のパターンのデザインを試してみてください。データにすると、形や色の変更は簡単にできますので、色や細かいサイズを変えてみて、よりイメージに近いものを選択しましょう。また、ロゴには通常多くの色を使わずに、1~2色で作成します。3色以上を使う場合には、配色ルールに基づいて色を選択し、彩度や明度のバランスを合わせることが必要です。
そして、ロゴで使用する文字のタイポグラフィを決めます。文字にどんなフォントを選ぶかもデザインの重要な要素で、ロゴを見た人に与える印象は大きく変わります。複数のフォントを試して比較してみてください。このとき、フォントによっては商用利用できない場合もありますので、フォントの著作権回りも調査したうえで選択しましょう。
◆ロゴ作成の専門業者に依頼する
ロゴを作成するにはパソコンが欠かせません。もし、パソコン操作が苦手なら、業者に依頼して作成してもらうのが良いでしょう。ロゴのコンセプトやイメージを伝えると、プロの手によって理想のロゴを作成してもらうことができます。
これまでに12000社以上のロゴを世に排出してきた安心の実績を持つLOGO市は、ロゴ作成に特化したデザイン作成サービスす。
また、LOGO市のオリジナルロゴ作成プランではロゴのご提案は無料。デザインが気に入らなければ料金は発生しませんので、はじめてのロゴ作成でも安心してご利用いただけます。
ロゴ作成の注意点

ロゴは商品や会社のシンボルイメージとなるものです。そのため、作成時には長く使えることと、さまざまな場面で使われることを想定しておく必要があります。ロゴ作成にあたり注意しておきたいポイントも確認しておきましょう。
今の流行にとらわれすぎない
ロゴは、企業やサービスのシンボルイメージとなるものですので、頻繁に変更するものではありません。通常、一度作成したら10~20年など、長い期間使うことになります。
流行のデザインは、洗練された印象を与えるかもしれません。しかし、今の流行にとらわれ過ぎてしまうと、流行が去ったあとに時代遅れな印象となってしまいますので注意しましょう。
特に、特殊な効果を狙ったロゴは、のちのち時代を感じさせてしまうことが多いので、避けておくのが無難です。時代によってロゴを変更する企業もありますが、かつてのロゴのイメージが強く、新しいロゴがなかなか定着しないという例もよく見られますので、ベストな手法とはいえません。
長期的に発展を続けている企業のロゴを見てみると、多くは流行とは関係のない、シンプルで普遍的なデザインとなっています。ロゴデザインを考える際には参考にしてみましょう。
作成するときのポイントは、感覚ではなくコンセプトをデザインに具現化することです。その点に注意しておけば、長く良いデザインとして愛されるロゴとなるでしょう。
様々な場面でロゴが使われることを意識
ロゴはそのまま企業やサービスのシンボルとなり、社内以外でも様々な場面で利用されるものです。結果、ロゴだけが使用され、ロゴのイメージが一人歩きして定着することも少なくありません。そのため、奇をてらったものではなく、企業やサービスのイメージや将来的な方向性を端的にあらわせるように意識してデザインしていきましょう。
また、後からトラブルとならないよう、完全にオリジナルで作成するようにします。最悪の場合、せっかく作成したロゴが使えなくなることや、企業イメージを大きく損なう可能性もあるからです。権利関係には十分に注意しましょう。
なお、ロゴはデザインしたカラーの状態だけでなく、白黒のみのビジネス文書で使用されることも多いです。そのため、カラーのロゴの場合、モノクロで印刷しても変わらないイメージで認識できるかといった点もチェックしておきたいポイントです。サイズを縮小したときや拡大したときにも、ロゴがきちんと認識できるか、イメージが大きく変わらないかもテストしてみてください。
はじめてのロゴ作成を楽しんでください!
いかがでしたか?以上、はじめてのロゴ作成に役立てほしいコツと注意点を紹介しました。
ターゲットやロゴのテイストを考えたり、ラフを作ってパソコンでデータにしたり、様々な工程が必要ですが、想いがこもって完成したロゴは愛着もわき、長年使っていくことができます。
自身で書いたラフスケッチをもとに、専門業者でロゴとしてデータ化してもらうのもおすすめです。そうすることで、プロによるロゴについてのアドバイスも踏まえながら、より一層納得のいくロゴを完成させることができるでしょう。