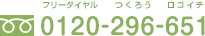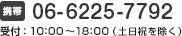会社ロゴの使い方|活用するためのポイントを解説
会社のロゴを作りたいと思ったははいいものの、どうやってロゴを活用したらいいかわからないと感じていませんか?
ここでは、会社のロゴが持つ役割をおさらい・目的にあったロゴの活用方法・活用しやすいロゴを作るポイントなどを解説していきます。ぜひ、この記事を参考にロゴ作成して上手に活用してくださいね。
会社ロゴの役割とは?

漠然と会社にはロゴが必要そうだとわかっていても、その役割を明確に説明できる人は意外と多くありません。文字だけではパッと伝えきれないイメージを伝えたり、会社のことをもっと身近に感じてもらったりと、会社のロゴには大切な役割があります。
ここでは、ロゴの重要性・必要性を改めておさらいしておきましょう。
会社の存在や商品の認知度を高める
周囲を見渡してみると、さまざまなところに会社や商品のロゴが使われているのがわかります。これは、視覚的にロゴを認知してもらい会社や商品を広く知ってもらうために、さまざまな会社が意図的にロゴを活用しているからです。
人間の脳は、文字よりも絵や画像の方が記憶に残りやすい性質があります。このため、さまざまな会社がオリジナルロゴを使って認知の拡大を目指しています。統一感のあるロゴを広く活用することで、会社や商品の存在を知ってもらう効果が期待できます。
会社や商品の価値を高める
『ロゴを見ただけで会社や商品をイメージできる』これがロゴ活用の理想ではないでしょうか。
ロゴの認知を広げて会社や商品を知ってもらい、会社や商品の信頼感を得て、最終的には消費行動に繋げていく。このように、ロゴはブランディングのツールとしても重要な役割を果たしており、会社や商品の価値を高める効果が期待できます。
人間は接触回数の多いものに好感を持ちやすい性質を持っているので、ロゴを上手に活用して認知を広げることで、会社や商品に対してのイメージ戦略にも繋がります。
会社がめざす方向性を社員と共有する
ロゴが持つ力は、社外に向けてだけでなく社内に向けても発揮されます。
ロゴを作成する際には、伝えたい想い・理念・コンセプトなどをデザインに活かしていますよね。これらを伝えたい相手は社外だけでなく、自社で働く社員にこそ知ってほしいもの。そんなときは、社内でも目に付くところにロゴを使用して社内への認知も広げるとよいでしょう。
社内に向けてロゴの認知を拡大し、その意味を理解してもらうことで、会社全体の進む方向性が明確になります。社員ひとりひとりがその方向性に沿った行動を意識することで、団結力や意識の底上げが期待できます。
会社ロゴの活用方法

会社のロゴを作成したら、どんどん活用してロゴに込めたメッセージをアピールします。ロゴを通じて会社のことを知っていただくチャンスですから、さまざまなところにロゴを使って社内・社外ともに印象づけるよう努めましょう。
とはいえ、どのように活用したらよいか用途があまり浮かばない…といった場合もあると思います。そこでここでは、ロゴ活用の目的からその方法まで具体的にご紹介していきます。
ロゴを活用する目的
大小さまざまな会社がオリジナルのロゴを定め、いろいろな場面で活用していますが、会社のオリジナルロゴを持つことには大きな目的があります。この目的をしっかり理解し、活用方法を考えてみるとよいでしょう。
社外に向けての発信
アパレルショップや飲食店、コンビニなど、世の中の会社は職種問わずオリジナルロゴを持っています。意識してみると、家の中も街の中も、ロゴで溢れかえっています。ロゴを見ただけでどの会社がわかったり、会社名を聞いたらロゴが浮かんでくるといったことも多いでしょう。
このように会社のロゴを広く認知してもらい記憶に残すことで、会社の認知度を高める効果が期待できます。文字よりも絵や画像の方が記憶に残りやすい人間の性質を上手に活用し、視覚的に会社をイメージしやすいロゴはとても重要です。
いろいろなところにロゴを活用し、ロゴ自体の認知を広げることは、会社の認知拡大に直結します。ですから、ロゴを幅広く知ってもらう工夫が必要です。
社内に向けての発信
会社の理念やコンセプトが込められたロゴは、社外だけでなく社内にもよい影響を与えます。なぜなら、日常的に目にするロゴを通じて会社の目指す姿を共有し、社員の意識向上や団結力・帰属意識の向上に繋げられるからです。
普段から目に付く場所にロゴを活用することで『自分も会社の一員である』という意識が生まれ、そのロゴに込められた意味を知ることで向かう方向性を示すことができます。働く仲間との共通認識として会社の理念・コンセプトが浸透すれば、会社全体が自然と同じ方向を向き、社員1人1人が飛躍するきっかけにもなります。
ロゴ活用の具体例
大切なロゴが完成したら、次はどんどん活用するのみ!ロゴの認知を広げて会社運営に役立てましょう。一般的な活用法としては、名刺や自社サイト、会社案内やカタログなどが挙げられます。
とにかく目に付くところにロゴ使って印象付けることが重要なので、ロゴ作成と合わせて著作権譲渡も行い、思いついたところにどんどん活用するといいでしょう。
・日常的に使う備品や文房具にロゴを入れて社員に使ってもらう
・営業で使うクリアファイルや見積書・納品書・請求書にロゴを入れる
・販促品としてロゴ入りのペンやカレンダー、エコバックなどを配る
・社用車にロゴをペイントする
・自社SNSのアイコンやトップページなどにロゴを入れる
・制服に刺繍でロゴを入れる
業種によってもかなり活用の幅は広がりますが、ロゴは汎用性が非常に高いので、ありとあらゆる場所に使えます。どんどん活用してロゴを人の目に触れさせることがとても重要なので、業務の中でよく使うものやお客様がよく目にする場所を探して積極的にロゴを使い、認知を広げましょう。
ロゴを適切に活用するために

会社のロゴを作成するときは、プロの制作会社に依頼してロゴを作成するのが最適です。デザイン性が高く理念やコンセプトをイメージできるロゴができあがるため、会社の顔としてロゴを活用するための必須条件と言ってもいいでしょう。
しかし、制作会社に依頼したらOKということではなく、実際にロゴを使う際のルールやポイントをおさえて、しっかりと確認しておきたいポイントがいくつかあります。
ここでは、会社のロゴを適切に活用するために確認しておきたいことをまとめたので、参考にしてください。
完成したロゴの著作権譲渡の確認
ロゴの作成を外部に依頼した場合にトラブルとなりやすいのが、著作権の問題です。
著作権とは、著作物(会社のロゴ)を作成した人(著作者)が著作物を独占的に利用できる権利のことをいい、特別な手続きがなくても著作者に対して自然発生します。著作物は、作者の考え・思想や、気持ち・感情を表現したもののことを指しており、学術・文学・美術・音楽の分野で著作者を守るための大切な権利です。
会社のロゴも著作物に含まれるので、完成したロゴの納品だけでなく、著作権が譲渡されるかどうかにも注意を払う必要があります。
著作権の譲渡は制作会社によってさまざま
将来のトラブルを未然に防ぐために重要な著作権譲渡ですが、その対応は依頼する制作会社によって大きく差があるのが現状です。著作権譲渡に5~10万円程度の別途料金を設けている会社や、著作権譲渡を行っていない会社もあります。
会社のロゴを広く活用するためにも著作権譲渡は必須条件ですが、制作会社によって認識が異なるため、正式に依頼する前に必ず確認しましょう。
LOGO市なら著作権譲渡も込みの料金で安心!
「LOGO市」では、ロゴの著作権譲渡について別料金を設けていません。ロゴは、完成したらお客様にどんどん使っていただいてはじめて役立つものだという考えから、すべてのご依頼について著作権の譲渡まで含めて「ロゴ作成」としています。
また、ご希望があれば、著作権の譲渡が行われたことの証明になる『著作権譲渡証明書』の発行も可能です。(オプション対応)著作権譲渡が適切に行われたことの証明になる文書なので、ロゴを作成する多くの会社に発行させていただいております。お気軽にご要望ください。
納品データの種類の確認
ロゴが完成し実際に納品される際は、データでの納品となることがほとんどで、この納品データを利用して、さまざまな場所にロゴを活用していくことになります。ここで確認しておきたいのが、納品されるデータ形式です。
実際にさまざまな場面でロゴを活用したいときには、外部に依頼することが多いでしょう。しかし、必要な形式でロゴのデータを持っていない場合、依頼を受けてもらえないことがあります。
以下に、最低限持っておきたいデータ形式をまとめました。どのような形式でデータが納品されるか、正式に依頼する前に確認しておきましょう。
AIデータ
AIデータは、Adobe(アドビ)社の「Adobe Illustrator」(アドビ イラストレーター)というアプリケーションで作成されたファイル形式です。
このデータは、ありとあらゆるデザインの現場で広く使われており、印刷物や看板などのデザインやサイト制作の際にも使われています。印刷会社や制作会社では、AIデータでの入稿を受け付けていることが多いため、AIデータは必ず持っておきたいデータ形式です。
PDFデータ
PDFデータは、専用のアプリケーションがなくても開ける「電子化された文書」のファイル形式です。
デザインの現場で汎用性の高いAIデータは、Adobe Illustratorがインストールされているパソコンでしか開けません。そのため、一般的なパソコンでもAIデータのデザインが確認できるように、PDFデータも持っておくと安心です。
JPEGデータ
JPEGデータは、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影された写真と同じファイル形式です。
普段画像を使うときと同じ使い方ができるので、資料に載せたりSNSのアイコンに指定したりといった手軽な場面であれば、誰でも簡単にロゴを活用できます。わざわざ外部に依頼しなくても活用の場を広げられるので、持っていると便利なデータ形式です。
ロゴデザインの確認
ロゴ作成を依頼する際には、ロゴに込めたい理念・コンセプトを固めて制作会社に伝えておくことが重要とされていますが、もしすでに決まっている活用方法があるようなら、これも必ず制作会社に伝えましょう。
制作会社のデザイナーは、会社の業種や理念・コンセプトだけでなく、ロゴの見え方・見られ方も意識してデザインを起こします。そのため、看板のような大きな場所で使いたい、制服の刺繍に入れたいといった実際の活用に関する情報は、ロゴの見え方を考えるうえで大切なポイントになるのです。
素敵なロゴを作るためにも、打ち合わせの際には使いたい場所などの用途を細かくデザイナーに伝えておくといいですね。
ロゴレギュレーションシートの確認
大切に作ったロゴの意味を広く周知し、適切な使い方で活用していくために必要なのがロゴレギュレーションシートです。
ロゴレギュレーションシートはロゴの取扱説明書のようなもので、ロゴに込めた理念・コンセプト、色・余白・大きさ・カタチなどが記載されていることが多く、実際にロゴを使用する際のガイドラインになります。
- 社内に向けてロゴに込めた理念・コンセプトを知ってほしい
- ロゴを使う際の最低限のルールを周知したい
- 販促品などを社外に依頼するたびにロゴに関する説明をするのが大変
こんなときは、ロゴレギュレーションシートが役に立ちます。ただし、対応は制作会社によってさまざまなので、事前に確認しておくのがおすすめです。
LOGO市ならロゴレギュレーションシートの作成にも対応!
「LOGO市」では、ロゴレギュレーションシートの作成にも対応しております。(オプション)
大切なロゴに込めた想いや、適切な使い方を手軽に周知する助けになるのが、ロゴレギュレーションシートです。統一感を損なわずにロゴを活用するために重要な文書なので、お気軽にご要望ください。
⇒ロゴレギュレーションシート詳細
ロゴ作成会社ならロゴ活用も一括対応

ロゴ作成から実際に活用するまで、注意点がいろいろあって大変だと感じた方もいるかもしれませんね。
ロゴの作成とロゴの活用を分けて考えると、間に入ったやり取りを面倒に感じることがあるかもしれませんが、ロゴ作成を手掛けている制作会社の中には、ロゴを使った販促品の制作にも対応している場合があります。この場合はやり取りの相手が一本化できるため、ロゴの作成から販促品の作成までノンストップで依頼ができて、さまざまな手間が省けて大変効率的です。
著作権譲渡・納品時のデータ形式・ロゴレギュレーションシートの3点については事前に確認が必要ですが、ロゴ作成から販促品制作までを一手に引き受けてくれる制作会社への依頼は、手軽にロゴを運用する助けになるでしょう。
LOGO市ならロゴ作成から販促品制作までノンストップでの依頼が可能!
「LOGO市」では、12000社以上のロゴを生み出してきた実績と、長年の経験で培ったロゴ制作のノウハウを生かして、さまざまな業種に対応したロゴを作成できます。ご希望の活用法に合わせたデザインの提示・必要なデータ形式のご提案もおまかせください。
- 著作権は納品時に無料で譲渡!必要に応じて著作権譲渡証明書の発行にも対応しています。
- AIデータはもちろん、PDF・JPEG形式も合わせて納品!ご希望の納品形式があればご相談ください。
- ロゴレギュレーションシート作成可能!あなたのロゴだけの取扱説明書をお作りします。
- ロゴ完成後の販促物制作もお任せください。名刺やウェブサイトなど各種対応しています。
まとめ:会社ロゴ活用のポイント
ここまで会社のロゴを活用する際のポイントをお伝えしてきました。簡単に内容をまとめておきましょう。
・会社のロゴを通して広く理念やコンセプトを伝えよう
・目に付くところにどんどん活用して認知拡大に努めよう
・著作権譲渡、納品データ形式、ロゴレギュレーションシートは依頼前に要確認
・ロゴ作成から販促品制作まで一手に依頼できる制作会社を見つけよう
会社のロゴは、多くの人の目に触れて理念・コンセプトを伝えるために大切なツールです。ロゴ作成の段階からどんなことに活用できるか想定しながら、準備を進めるとよいでしょう。
なかでも、著作権譲渡、納品データ形式、ロゴレギュレーションシートの3点はロゴ作成を依頼する時点でしっかりと確認し、実際にロゴを活用する際に手間取らないように注意したいポイントです。ロゴ作成から実際の活用するまでを一手に引き受けてくれる制作会社に依頼することで、さまざまなやり取りが省略できますよ。どんどん活用していくことを前提に、ロゴ作成を依頼するようにしましょう。